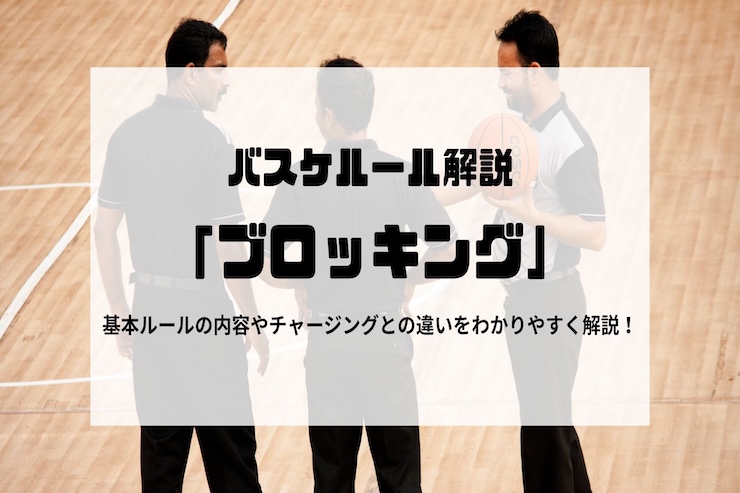こんにちは!
NBA好きブロガーのおしょうサンドです。
バスケの反則(ファウル)の1つである「ブロッキング」。
存在はなんとなく理解しているものの、その正確な条件まで把握している方は意外と少ないのではないでしょうか?
この記事では、そんな「ブロッキング」についての基本的なルールの内容についてまとめていこうと思います。
非常に見分けが難しい「チャージング」との見分け方についても解説していきますので、正確なルールを知りたいという方はぜひ最後までご覧くださいね!
それではさっそく、ティップオフ!!
目次
ブロッキングとは?
バスケの「ブロッキング」とは、その名の通り、体を使って相手のプレイヤーの進路をブロックする行為に対する反則。
腕や足など、体のどの部位を使ったとしても相手の進路を妨げた場合には適応されますよ。
基本的にはディフェンス側の選手に適応されることが多い反則で、選手同士の衝突など危険な状況になるのを防ぐために作られたルールです。
ブロッキングが発生した際には、相手チームにフリースローやスローインの権利が与えられる流れになります。
ブロッキングとなるシチュエーションの例を紹介
先述したように、ブロッキングはディフェンス側の選手に適用されることが多い反則です。
よくあるシチュエーションとしては、ドライブで切り込んできた選手に対するディフェンスがありますね。
ドライブに対して少し反応が遅れ、後から無理に進路へ入り込んだ結果ブロッキングになってしまうというケース多いです。
ブロッキングとチャージングは紙一重!違うポイントを2つ紹介
「ブロッキング」とよく似たシチュエーションでコールされる反則に「チャージング」というものがあります。
どちらにしても選手同士が衝突した際に適応されるものなのですが、「ブロッキング」がディフェンス側の選手に適応されることが多いのに対して、チャージングはオフェンス側の選手に適応されることが多い反則です。
判断に重要なのは「ディフェンスが先に動き出したかどうか」という点。
ディフェンスがオフェンスの進路に遅れて横入りしている場合は「ブロッキング」、先周りして進路を塞いだにも関わらずオフェンスが突っ込んだ場合は「チャージング」といったところでしょう。
さらに詳しく「ブロッキング」か「チャージング」かを見分けるためには、ディフェンス側の姿勢に関する以下の2つのポイントを理解する必要がありますよ。
【ブロッキングかチャージングかを見分けるポイント2選】
- リーガルガーディングポジションをとれているか
- シリンダーから外れていないか
この後詳しく見ていきましょう!
ポイント①衝突した時点でディフェンスが「リーガルガーディングポジション」を取れているか?
ブロッキングとチャージングを見分けるポイントの1つ目は、ディフェンスが「リーガルガーディングポジション」をとれているかどうかです。
「リーガルガーディングポジション」とは、簡単い言うと、両足をついた状態でオフェンスの進行方向に対して正対した姿勢のこと。
ディフェンスが遅れて動き出した場合、ドライブの進行方向に対して正対することができないため、ブロッキングという判定になるわけですね。
逆に、ディフェンスが先にドライブの進行方向に入り込めている場合、正対したディフェンスにオフェンスが突っ込む形となり、チャージングの可能性が高まることになります。
ただ、これだけではチャージングと断定することはできず、この後解説するポイント②も満たす必要がありますよ。
公式ルールブックの「リーガルガーディングポジション」の解説の部分を載せておきますので参考にしてください。
33-3 リーガルガーディングポジション
ディフェンスのプレーヤーは以下の2つの条件を満たしたとき、リーガルガーディングポジションを占めたとみなされる。
・相手チームのプレーヤーに正対する。
・両足をフロアにつける。リーガルガーディングポジションには真上の空間も含まれるので、真上の空間の内側であればまっすぐ上に手や腕を上げたりジャンプしても良いが、シリンダーの外に外れてはならない。
ポイント②衝突した時点でディフェンスが「シリンダー」から外れていないか?
続いて、2つ目のポイントであるディフェンスが「シリンダー」から外れていないかについて解説していきます。
「シリンダー」ってなに?
そもそも「シリンダー」についてちゃんと知っている人の方が少ないのではないでしょうか。
バスケにおける「シリンダー」とは、プレイヤー一人ひとりに設定された”円筒状”の架空の空間のこと。
フィールド上における選手それぞれの”パーソナルスペース”のようなもので、この空間を超えて相手選手に不当に接触すると「ファウル」になるという原則があります。
「シリンダーの概念」について公式の定義を載せておきますが、正直覚える必要はないと思います。
ルール上で判断しやすいように、”選手一人ひとりを円筒状のポールとして扱おうとしているんだな”ということが分かっていただければ大丈夫です。
33-1 シリンダーの概念
シリンダーとはコート上のプレーヤーが占める架空の円筒内の空間をいう。シリンダーの大きさ、あるいはプレーヤーの両足の間隔はプレーヤーの身長やサイズによって異なる。シリンダーにはプレーヤーの真上の空間が含まれ、ディフェンスのプレーヤーとボールを持っていないオフェンスのプレーヤーのシリンダーの境界は以下の通り制限される:
・正面は手のひらの位置まで。
・背面は尻の位置まで。
・側面は腕と脚の外側の位置まで。手や腕は、前腕と手がリーガルガーディングポジションの範囲で上がるように、腕を肘の位置で曲げた状態で前に伸ばすことができるが、足や膝の位置を超えてはならない。
「2025 バスケットボール競技規則」にはシリンダーのイメージイラストも貼ってありましたので、文面だけでイメージできないという方はイラストを確認してみてくださいね!
ポイント①と②の両方を満たす必要がある
さて、ここからはこの「シリンダー」がブロッキングとチャージングの見分け方にどう関係しているのかについて解説していきますよ!
先述したように、ディフェンス側がオフェンスからチャージングを獲得するためには、オフェンスのドライブの進行方法に「リーガルガーディングポジション」で立っている必要があります。
ただし、ただ「リーガルガーディングポジション」で立っているだけでは不十分であり、さらに”シリンダーから外れていない”という条件を満たす必要があるというわけですね。
そもそも”シリンダーから外れる”とは、身体の一部が空想上の円筒から外に出てしまっている状態のこと。
腕を前や横に突き出したり、足を前後に開いたりした状態は”シリンダーから外れている”と判断されてしまうということです。
たとえ「リーガルガーディングポジション」で立っていたとしても、シリンダーから外れた状態でオフェンスと衝突した場合は、ディフェンス側の「ブロッキング」となります。
一方、両手を上げたり、腰を落として一般的なディフェンスの姿勢をとったりした状態であれば、”シリンダーから外れていない”と判断することができます。
「リーガルガーディングポジション」で立ち、かつシリンダーから外れていない状態でオフェンスと衝突して初めて、オフェンス側の「チャージング」が宣言されるわけです。
ちなみに、オフェンスとの距離を一定に保つために後ろに下がることは”シリンダーから外れた”とはみなされないそうです。
まとめ
今回はバスケットボールの「ブロッキング」について解説してきました。
いかがでしたでしょうか?
この記事のポイントは以下の5つです。
【この記事のポイント5選】
- 「ブロッキング」とは、体を使って相手のプレイヤーの進路をブロックする行為に対する反則のこと。
- 「ブロッキング」が発生した際には、相手チームにフリースローやスローインの権利が与えられる。
- 「ブロッキング」とよく似た反則に「チャージング」がある。
- オフェンスとの衝突時にディフェンス側が「リーガルガーディングポジション」をとれていなければ「ブロッキング」となる。
- オフェンスとの衝突時にディフェンス側が「リーガルガーディングポジション」でかつ「シリンダーから外れていない」姿勢をとれていれば「ブロッキング」は取られない。
「ブロッキング」と「チャージング」は時にゲームの勝敗を分ける判定でありながらも、本職の審判ですら判断を誤ることがあるほどに見分けるのが難しい反則です。
プレイヤーの方はルールをしっかりと把握する必要がありますが、バスケ観戦をする時はその判定がどちらになるのかをドキドキしながら待つというのも楽しみ方の1つではないでしょうか?
それではまた、次の記事でお会いしましょう!!