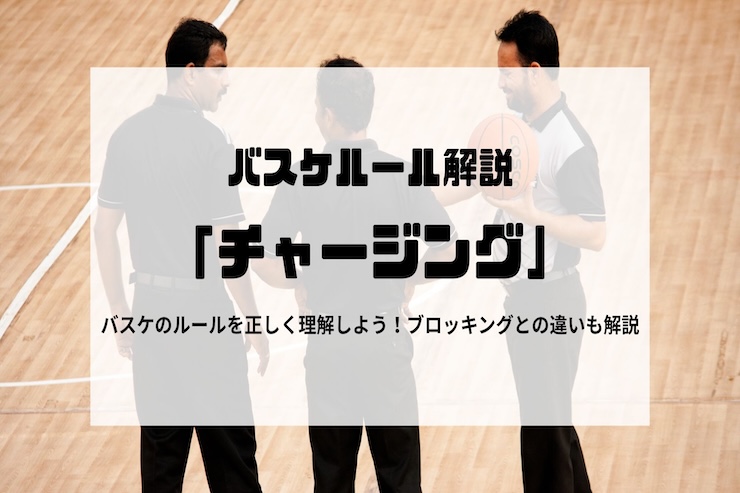こんにちは!
NBA好きブロガーのおしょうサンドです。
バスケットボールの反則(ファウル)の1つである「チャージング」。
接触の多いスポーツであるバスケットボールにおいてオフェンスの接触を制限する重要なルールですが、その詳細を正確に知っている方はそれほど多くないのではないでしょうか?
この記事ではそんなバスケの「チャージング」について、ルールの内容はもちろん、判別の難しい反則である「ブロッキング」との見分け方などについて解説していこうと思います。
バスケ未経験の方にもわかりやすいと思っていただけるように解説していきますので、正確なルールを把握したい方はぜひ最後までご覧くださいね!
それでは早速、ティップオフ!!
目次
「チャージング」とは?
バスケの「チャージング」とは、オフェンスの選手が相手ディフェンスを不当に攻撃することを防ぐための反則です。
別名”オフェンスチャージング”とも呼ばれ、ディフェンスの選手に強くぶつかったり、手で押しのけたり、押さえつけたりするなどの行為が反則に該当しますよ。
”オフェンス”というと何となくドリブルしている選手をイメージしがちですが、ボールを持っていない選手でも同様な行為をした場合は「チャージング」となります。
例えば、ボールを受け取るために相手ディフェンスを手のひらや腕で押さえつけた場合にはチャージングになる可能性が高いでしょう。
もしチャージングがコールされた場合は、罰則として相手チームにフリースローやスローインが与えられます。
「チャージング」と「ブロッキング」との違いは何?
「チャージング」とよく似たシーンで起こるファウルに「ブロッキング」というものがあります。
どちらも選手同士が衝突した際に適応されるものですが、「チャージング」がオフェンス側の選手に適応されることが多い反則なのに対して、「ブロッキング」はディフェンス側の選手に適応されることが多い反則。
チャージングと同様に、相手選手がボールを持っているかどうかは関係なく、主にオフェンスの進路を妨げたり、横から腕を伸ばしてプレーを妨害するなどの行為に対して罰則を与えるものです。
「チャージング」と「ブロッキング」の判断は非常に難しく、プロの審判でも誤審になることがあるほどです。
具体的な判断基準についてはこの後解説しますので、ルールを深く知りたいという方はぜひ目を通してくださいね!
見分けるのが難しい!チャージングとブロッキングの判断基準を解説
先述したように、「チャージング」と「ブロッキング」はどちらもオフェンスとディフェンスの選手同士が接触した際に宣せられる反則です。
スピードに乗った状態での一瞬の駆け引きを正確に判断するのは非常に難しいと言えるでしょう。
ただ、当然オフェンスとディフェンスのどちらが反則かを決める判断基準は存在しますよ。
ここでは、そんな「チャージング」と「ブロッキング」を見分けるための判断基準を2つ解説していこうと思います。
判断基準①ディフェンス側のポジションどり
「チャージング」と「ブロッキング」を見分けるための判断基準の1つ目は「ディフェンス側のポジションどり」です。
ディフェンスがオフェンスの進路内にポジション取りができているかどうかが重要ということですね。
ディフェンスが先に動き出してオフェンスの進行方向を塞いでいた場合は「チャージング」。
逆にディフェンスが遅れて反応し、オフェンスの進行方向へ後から入り込んできた場合は「ブロッキング」といった形で判定されますよ!
よく”ディフェンスが止まっていればチャージングにならない”という方がいますが、止まっているかどうかよりもオフェンスの進行方向にポジション取りができているかの方が重要みたいですね。
ちなみに、これは空中でも同じことが言えます。
先にオフェンスが踏み切る前にディフェンスがオフェンスの進行方向を塞いでいた場合は「チャージング」。
オフェンスが踏み切った後にディフェンスがコースに入り込んできた場合は「ブロッキング」になるというわけです。
また、ディフェンス側の動きにおいてもう一つキーワードとなるのが「リーガルガーディングポジション」です。
「リーガルガーディングポジション」とは”両足をついた状態でオフェンスの進行方向に対して正対した姿勢のこと”で、進行方向にポジショニングしていたとしても、体の側面がオフェンスの方を向いていてはチャージングにはならないということですね。
何かとディフェンス側に厳しいルールになっていますが、さらにもう一つ、次に解説する条件を満たす必要がありますよ。
公式ルールブックの「リーガルガーディングポジション」の解説の部分を載せておきますので参考にしてください。
33-3 リーガルガーディングポジション
ディフェンスのプレーヤーは以下の2つの条件を満たしたとき、リーガルガーディングポジションを占めたとみなされる。
・相手チームのプレーヤーに正対する。
・両足をフロアにつける。リーガルガーディングポジションには真上の空間も含まれるので、真上の空間の内側であればまっすぐ上に手や腕を上げたりジャンプしても良いが、シリンダーの外に外れてはならない。
判断基準②「シリンダー」の範囲から外れていないか
「チャージング」と「ブロッキング」を見分けるための判断基準の2つ目は「『シリンダー』の範囲から外れていないか」です。
バスケにおける「シリンダー」とは、プレイヤー一人ひとりに設定された”円筒状”の架空の空間のこと。
フィールド上における選手それぞれの”パーソナルスペース”のようなもので、この空間を超えて相手選手に不当に接触すると「ファウル」になるという原則があります。
ディフェンス側がチャージングを撮るためには身体の全てがこのシリンダーの内側になければならないということです。
正直シリンダーの概念について正確に把握する必要はないと思いますが、少なくとも手を大きく前や横に出したり足を前後に開いたりした状態ではチャージングは取れないということは理解しておきましょう。
逆に言えば、ディフェンス側はこのシリンダーないであれば自由な体制を取ることができますよ。
例えば、両手を上げてシュートを打たせないようにする行為はシリンダーの中から出ていないため、そのままの体制で接触があったとしてもオフェンスのチャージングになる可能性があるということですね!
チャージングがとられない?例外的なシーンを2つ紹介
ここまで「チャージング」の主なルールの内容とよく似たルールである「ブロッキング」との違いについて解説してきました。
「チャージング」って複雑だなと感じた方も多いのではないでしょうか?
だた、もう一つだけ、チャージングにおいて知っておかなければならないことがあります。
それが一見チャージングのように見えるものの、実はチャージングと判定されないケース。
ここでは、そんな例外的なシーンを2つ解説していこうと思いますよ!
ゴール下の「ノーチャージセミサークル」で接触した場合
1つ目の例外は、ディフェンスとの接触がゴール下にある「ノーチャージセミサークル」にて行われた場合。
ノーチャージセミサークルとは、ゴールの下に描かれている半円状のラインのこと。
コートにおいては、他とは違う色で塗られている「ペイントエリア」のさらに内側に引かれています。
この線がなぜ「ノーチャージセミサークル」と呼ばれているかというと、その名の通り、その線より内側では「チャージング」が取られないからです。
シュート体制に入ることが予想されるエリアでは、オフェンスが有利に動けるようなルールになっているということですね!
ただ、「ノーチャージセミサークル」の中であれば何をしても許されるというわけではありません。
チャージングにならないためには以下の条件を満たしている必要がありますよ!
【ノーチャージセミサークル内でチャージングにならない条件】
- 空中でボールをコントロールしている
- シュートまたはパスの体制に入っている
- 接触したディフェンスプレーヤーの片足または両足が、ノーチャージセミサークル内またはライン上にある
あくまでシュートやパスの体制でなければならず、単にディフェンスを手で押さえつけるなどのプレーはちゃんとファウルになるというわけですね。
また、チャージング以外の反則は当然適応されますので注意が必要ですよ。
オフェンスが故意にディフェンスのファウルを誘った場合
2つ目はオフェンスが故意にディフェンスのファウルを誘った場合。
これはチャージングの枠には収まらず、オフェンスファウルを取られる可能性があるということですね。
また、ディフェンスに怪我を負わせかねないような悪質なプレーの場合は「アンスポーツマンライクファウル」や「ディスクォリファイングファウル」といったさらに高いレベルの罰則を与えられる可能性もありますよ。
故意にディフェンスのファウルを誘う例としては、明らかに不可解な角度からディフェンダーに向かってドリブルを仕掛けたり、当たっていないにも関わらず殴られたそぶりを見せたりするなどが当てはまりますね。
このようなシーンは滅多に見られることはないですが、スポーツマンシップに則ったプレイを徹底するようにしましょう。
まとめ|バスケの「チャージング」とは?細かなルールを正しく理解しよう
今回はバスケの「チャージング」について解説してきました。
いかがでしたでしょうか?
この記事のポイントは以下の5つです。
【この記事のポイント5選】
- 「チャージング」とは、オフェンスの選手が相手ディフェンスを不当に攻撃することを防ぐための反則のこと。
- 「チャージング」が発生した際には、相手チームにフリースローやスローインの権利が与えられる。
- 「チャージング」とよく似た反則に「ブロッキング」がある。
- ディフェンスとの接触時にディフェンスが先に動き出してオフェンスの進行方向を塞いでいた場合は「チャージング」となる。
- ディフェンスとの接触がゴール下にある「ノーチャージセミサークル」にて行われた場合は基本的に「チャージング」にならない。
「チャージング」と「ブロッキング」は時にゲームの勝敗を分ける判定でありながらも、本職の審判ですら判断を誤ることがあるほどに見分けるのが難しい反則です。
プレーヤーの方はルールをしっかりと把握する必要がありますが、バスケ観戦をする時はその判定がどちらになるのかをドキドキしながら待つというのも楽しみ方の1つではないでしょうか?
それではまた、次の記事でお会いしましょう!!