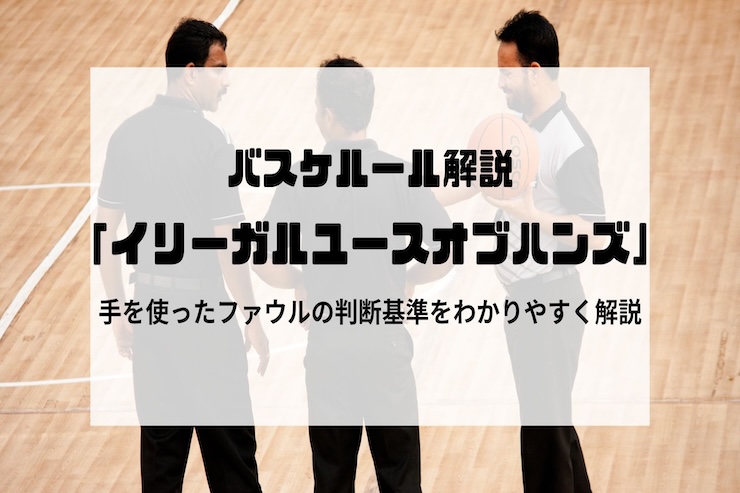こんにちは!
NBA好きブロガーのおしょうサンドです。
バスケットボールの反則(ファウル)の1つである「イリーガルユースオブハンズ」。
直訳すると”違法な手の使い方”でしょうか。笑
接触の多いバスケットボールにおいて、選手同士の接触に関するルールは非常に複雑に定められています。
今回はそんな「イリーガルユースオブハンズ」について、反則の内容はもちろん、試合中に起きる具体的なシーンやオフェンス・ディフェンス時に注意すべきことなどを解説していきますよ。
バスケ未経験の方でもわかりやすいと思っていただけるように解説していきますので、ルールを正確に把握したい方はぜひ最後までご覧くださいね!
それでは早速、ティップオフ!!
目次
イリーガルユースオブハンズ(illegal use of hands)とは
「イリーガルユースオブハンズ(illegal use of hands)」とは、手を使った不当な接触を禁止する反則です。
”手を使った不当な接触”とは、手のひらや腕、ひじなどを使った「つかむ」、「はたく」などの行為のこと。
かつては相手の手をはたくことを取り締まる「ハッキング」という反則がありましたが、現在は手を使った接触をまとめて禁止する「イリーガルユースオブハンズ」に統合されていますよ。
「イリーガルユースオブハンズ」が宣言されると、罰則として相手チームにフリースローやスローインが与えられます。
ハンドチェッキング(ハンドチェック)ってなに?
「ハンドチェッキング(ハンドチェック)」とは、故意に手で相手に触れる行為を禁止する反則のことです。
具体的にはボールを持っている相手プレーヤーに両手で触れる、片手でも伸びた肘で触れ続ける、短時間でも何度も触れるといった行為が該当するようですね。
ハンドチェッキングは相手プレーヤーのボール運びやシュートの機会を制限する行為であり、フェアプレーではないためファウルとなっていますよ。
これは豆知識ですが、NBAでは2004-05シーズンから「ハンドチェック」が禁止になっており、ディフェンス側の選手はオフェンスの選手の身体に触れることができなくなりました。
これにより機動力の高いガードのスター選手が台頭し始め、逆に機動力のないビックマンが活躍しづらくなったと言われています。
イリーガルユースオブハンズが適用される実際のプレーを解説
「イリーガルユースオブハンズ」が実際の試合で適用されるのは以下のようなシーンです。
- 相手のショットクロックをブロックしに行ったが、誤って手を叩いてしまった。
- ゴールしたのポジション争いにおいて、相手の身体を手で押したり引っ張ったりしてしまった。
- ボールをドリブルしていない方の手でディフェンスを押し除けた。
- 特に不当ではない相手の手を過剰に振り払った。
「イリーガルユースオブハンズ」はバスケのファウルの中でも特に審判による個人差が大きいルールだと言われています。
上で紹介したシーンでも、シューターがシュートの時に故意に腕を振り下ろしていた場合はオフェンスのファウルになることもありますし、相手の身体に触れていたとしてもそれが相手の行動を阻止していないと判断されればとくに問題視されません。
これらの判断には明確な基準がなく、実際にプレーする際はその日の審判が下したジャッジが基準になるということですね。
イリーガルユースオブハンズはどうやって判断する?ファウルの基本的な考え方を解説
ここまでで「イリーガルユースオブハンズ」がどのような反則なのかは分かっていただけたと思います。
”どこまでがファウルになるのか”という細かな判断は審判によって異なるため、ここで解説することはできません。
ただ、「イリーガルユースオブハンズ」が何のためにあるのか、なぜ必要なのかについては公式ルールブックに書かれています。
この基本的な考え方に基づいたプレーを行うことができれば、自ずとファウルの判断もできるようになのではないでしょうか?
公式ルールにおいて、「イリーガルユースオブハンズ」の基本的な考え方はこのように記されています。
プレーヤーが相手チームのプレーヤーに手や腕で触れることがあっても、必ずしもファウルではない。
審判は、プレーヤーが相手チームのプレーヤーに手や腕で触れたり触れ続けたりしていることで、触れ合いを起こしたプレーヤーが有利になっているか否かを判断し、相手チームのプレーヤーの自由な動き(フリーダムオブムーブメント)を妨げているときには、ファウルの判定を下す。
引用:2025 バスケットボール競技規則 33-11
イリーガルユースオブハンズを回避するためにオフェンス・ディフェンスで気を付けること
最後に「イリーガルユースオブハンズ」を回避するために気をつけるべきことを「オフェンス」、「ディフェンス」それぞれで解説していこうと思います。
ディフェンスの場合のイリーガルユースオブハンズ(手・腕・肘)
ディフェンスにおいては、以下のような場面で「イリーガルユースオブハンズ」が適用される可能性がありますよ。
【ディフェンスの場合のイリーガルユースオブハンズ】
- ボールを持つプレーヤーに両手で触れる
- ボールを持っているプレーヤーに肘が伸びた状態の手で触れ続ける。(片手でもNG)
- ボールを持っているプレーヤーに長時間触れ続ける。
- ボールを持っているプレーヤーに短時間であっても何度も触れている。
- ポストプレーに対するディフェンスにおいて、シリンダーから大きく外れた位置でアームバー(腕で相手の体を押す行為)を行う。
- オフェンスを腕や肘、手のひらでがっちり掴む(ロックする)。
- スクリーンプレーに対してスクリーンを押し除けるために手や腕を使う。
- スクリーンプレー対してスクリーンやハンドラーの動きを止めるために手や腕を使う。
先ほど引用した公式ルールにも書かれていたように、手や腕で触れること全てがファウルになるわけではありません。
ただ、その手や腕が相手のプレーヤーの動きを阻害する目的と受け取られた場合にはファウルを取られるため注意が必要ですね。
オフェンスの場合のイリーガルユースオブハンズ(手・腕・肘)
オフェンスにおいては、以下のような場面で「イリーガルユースオブハンズ」が適用される可能性がありますよ。
【オフェンスの場合のイリーガルユースオブハンズ】
- ボールを持ったプレーヤーがディフェンスを抜くために手や腕で相手を押したり掴んだりした。
- ボールを持っていないプレーヤーがディフェンスのプレーヤーを手や腕で掴んで抑えた。
- ボールを持っていないプレーヤーが手や腕をディフェンスのプレーヤーの腕に巻きつけた。
- ボールを持っていないプレーヤーがボールを受け取るために”シリンダー”から外れた位置でディフェンスを押さえつけた(ロックした)。
ただ、オフェンスの場合は「イリーガルユースオブハンズ」をするよりもされる方が多いかもしれませんね。
バスケはプレーヤー同士の接触が多いスポーツであり、特に手の接触は1試合の中で何度もあるはず。
審判も目は光らせているものの、すべての接触をジャッジすることは難しいと思います。
オフェンス側が「イリーガルユースオブハンズ」を行うことは当然避けるべきですが、シュートやドリブルは多少の接触があることを前提に練習をすることが大切と言えるかもしれませんね。
まとめ
今回はバスケの「イリーガルユースオブハンズ」について解説してきました。
いかがでしたでしょうか?
「イリーガルユースオブハンズ」は判定そのものが難しく、審判によって最も基準に差が出る反則だと思います。
特にディフェンスの時には、相手に一度も触れることなく攻撃を防ぐなんてできるはずがありませんよね。
多少の接触は見逃しつつも、スポーツマンシップに反するような行動は規制するために、あえて曖昧なルールになっているのかもしれませんね。
観戦する際にはそんな不確定なところもバスケットボールの面白さだと思って楽しんでみてはいかがでしょうか?
それではまた、次の記事でお会いしましょう!!