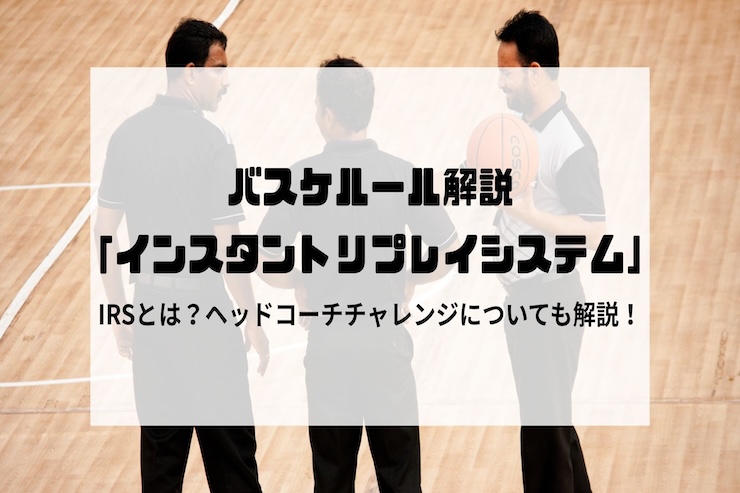こんにちは!
NBA好きブロガーのおしょうサンドです。
バスケ観戦中にチームのヘッドコーチが審判に対してビデオレビューを要求しているシーンを見たことがありませんか?
これは「インスタントリプレイシステム(IRS)」と呼ばれる2022年度から導入された新システム。
人間の目では判定が難しい場面をリプレイを見ることで正確に判定するためのものです。
同時に新設された「ヘッドコーチチャレンジ」というルールも、今後のバスケットボールにおいて試合を左右する重要な戦術となることは間違いありません。
これらのルールを正しく理解することで、バスケ観戦をより楽しめるはず!
そこで、この記事では「インスタントリプレイシステム(IRS)」の仕組みや「ヘッドコーチチャレンジ」のルールについて詳しく解説していこうと思います。
FIBA(国際バスケットボール)とNBAでの違いについても解説していますので、気になる方は施肥最後までご覧くださいね!
それでは早速、ティップオフ!!
目次
インスタントリプレイシステム(IRS)とは?簡単に解説
インスタントリプレイシステム(IRS)とは、試合の展開を左右する様々な場面において審判が下した判定に対し、異議申し立てや再確認の要請をすることができるシステムの総称です。
インスタントリプレイシステム(IRS)が導入されている大会では大会主催側が試合全体を通して自動録画を行なっており、必要となった場合にその動画の一部を切り取って確認することができるようになっているんですよ!
IRSで使用される録画機材はFIBA(国際バスケットボール連盟)に承認されたものでなけらばならないので、大会によっては機材が用意できずにIRSがない場合もあるようです。
「インスタントリプレイシステム(IRS)レビュー」とは?
「インスタントリプレイシステム(IRS)レビュー」とは、審判がIRSを利用して自身の下した判定を確認することを言います。
この確認を行う際には試合が一時中断し、専用のリプレイモニターにて審判団による確認作業が行われるんですよ!
実際の試合では重要な局面に行われることが多いので、観戦しているファンにとってもドキドキの瞬間となっています。
一見新しいルールに見えるIRSレビューですが、実は初めて導入されたのが1986年。
しかし、当時の映像技術では確認の限界もあり、試合時間が大幅に遅延することから1991年には一度廃止されています。
その後、現代のシステムに近い形で再導入されたのが1999年のこと。
近年ではリプレイ判定の適応範囲も広がったことで、バスケの重要な戦術の1つとして幅広く利用されるようになっていますね。
最終的な判定は”主審”が下す
インスタントリプレイシステム(IRS)レビューが行われると、審判団がフィールド脇に設置されたリプレイモニターの前に集まり映像の確認が行われます。
この時、審判団の他にも別室で待機している「リプレイアシスタント」も判定の助言を行なっているんですよ。
ただ、映像を確認したのちに最終的な判定を下すのは”主審”。
試合の勝敗を左右する重要な判定ですので、大きな責任が伴う役職ですね。
これは豆知識ですが、この判定はIRSレビューがコールされたのち「90秒以内」に発表されるルールとなっています。
インスタントリプレイシステム(IRS)レビューができる状況を紹介
ここまで「インスタントリプレイシステム(IRS)レビュー」の概要についてお伝えしてきました。
試合をより面白くしてくれる、非常に重要なルールですよね。
そんな「IRSレビュー」ですが、”どんなことを確認したいのか”によって要求できる状況が異なることをご存知でしょうか?
ここでは大きく以下の3つに分けて、「IRSレビュー」ができる状況を簡単に解説していこうと思います!
【IRSレビューが要求できる状況3選】
- クォーターやオーバータイムの終了時
- ゲームクロックが残り2分以下のとき(第4Q、オーバータイムのみ)
- ゲーム中あらゆる時間帯
状況①クォーターやオーバータイムの終了時
まずは「クォーターやオーバータイムの終了時」に要求が可能なレビュー内容についてです。
この状況で要求できる主な内容は以下の2つがありますよ。
- 各クォーターやオーバータイムが終了のブザーがなった時、最後のショットがブザーよりも先に放たれていたかどうか。
- 反則が起きた際に各クォーターやオーバータイムの残り時間が何秒からスタートするか。
2つ目の内容については、該当する反則として「アウトオブバウンズ」、「24秒バイオレーション」、「8秒バイオレーション」、「その他のファウル」などがあります。
状況②ゲームクロックが残り2分以下のとき(第4Q、オーバータイムのみ)
次に、第4クォーターとオーバータイムに限り「ゲームクロックが残り2分以下のとき」に要求が可能なレビュー内容についてです。
この状況で要求できる主な内容は以下の5つがあります。
- 試合終了のブザーがなった時、最後のショットがブザーよりも先に放たれていたかどうか。
- シュートがショットクロックの終了よりも先に放たれていたかどうか。
- シュートを打ったプレイヤーに関わっていない場所で起きたファウルがシュートよりも先に起きたものかどうか。
- 「ゴールテンディング」や「インターフェアレンス」といったバイオレーションが正しくコールされているかどうか。
- アウトオブバウンズ(ボールがコートの外に出ること)の際に最後に触ったプレイヤーを特定するため。
状況③ゲーム中あらゆる時間帯
最後に、「ゲーム中あらゆる時間帯」で要求が可能なレビュー内容についてです。
この状況で要求できる主な内容は以下の6つがあります。
- 成功したゴールのショットが2点か3点か。
- シューターへのファウルによってシュートが失敗した場合、フリースローが2本か3本か。
- 「パーソナルファウル」、「アンスポーツマンライクファウル」、「ディスクォリファイングファウル」、「テクニカルファウル」の判定が正当かどうか。
- ゲームクロックやショットクロックの誤作動が起きた場合、正しく訂正された時間が正当かどうか。
- フリースローを打つべきプレイヤーを特定するため。
- 乱闘などが起きた際に関わった人物を特定するため。
2023年に新設された「ヘッドコーチチャレンジ」とは?
試合を観戦していると、チームのヘッドコーチが審判に対して「インスタントリプレーシステム(IRS)」での判定確認を要求しているシーンがよく見られます。
これは「ヘッドコーチチャレンジ」と呼ばれ、ヘッドコーチにのみ許された権利の1つ。
FIBAのルールにおいてはIRSが導入されているすべての試合において、ヘッドコーチチャレンジが認められているんですよ!
そして、実は「ヘッドコーチチャレンジ」が2023年に新たなルールとして更新されたのをご存知ですか?
ここでは、より試合を面白くするために改定された「ヘッドコーチチャレンジ」について、「FIBA」と「NBA」の2つに分けて解説していこうと思います。
要求できる条件や回数など意外と知らない方も多いと思いますので、しっかりルールを把握したい方はぜひ参考にしてくださいね!
FIBA(国際バスケットボール連盟)の「ヘッドコーチチャンレンジ」
まずはFIBAが定める「ヘッドコーチチャンレンジ」に関するルールを解説していこうと思います。
2025年9月時点で、日本の国内リーグである「Bリーグ」はこのFIBAルールに準じて試合が行われているようですね!
FIBAルールにおいて、ヘッドコーチチャンレンジが使用できるのは1ゲームで1回のみ。
成功するかどうかに関わらず、1度使用したらそのゲーム中に使用することはできません。
ただし時間帯の制限はなく、正規の内容であればあらゆる時間で要求することができますよ!
知っておくべき重要な条件としては、ヘッドコーチチャレンジを要求する時点でチームの「タイムアウト」が残っている必要があるということ。
これはヘッドコーチチャレンジチャレンジが使用されると同時にタイムアウトが1回分消費されるためですね。
このタイムアウトは、判定が覆った場合チームに返却され、判定が覆らなかった場合はそのまま消費されます。
無駄なチャレンジの要求を防ぎつつ、正当なチャレンジには敬意を表した素晴らしい仕組みだと思いませんか?
要求する際には、ヘッドコーチ自身が最も近くにいる審判に対して見えるようにはっきりと要求する必要があります。
動作としては、大きな声で「チャレンジ!!」と言いながら「ヘッドコーチチャレンジシグナル」と呼ばれるジェスチャーをします。
「ヘッドコーチチャレンジシグナル」は頭の上に両手で長方形を描く動きで、みなさんもよく見たことがあるのではないでしょうか?笑
この要求をした時点でヘッドコーチチャレンジが発動されたこととなり、後から取り消すことはできないというのも知っておきましょう!
この要求を受けた後、審判は両チームにとって不利な状況にならない形で速やかにゲームを止める義務があります。
ゲームが止まったら、ヘッドコーチから審判にレビューを要求する判定が伝えられ、IRSレビューが行われるという流れですね。
レビューの時間は90秒で、その間プレイヤーは一時ベンチに下がります。
タイムアウトを使用していますので、当然レビューの間で作戦会議をすることも可能ですよ。
審判団が請求されたチャレンジに対して判定下し、状況を訂正した上で試合が再開となるわけです。
NBAの「ヘッドコーチチャンレンジ」
続いて、アメリカの男子プロバスケットボールリーグ「NBA」におけるヘッドコーチチャレンジのルールを解説していきます。
NBAは世界最高峰のバスケットボールリーグですが、他のリーグよりもエンタメ性を重要視しているため独自のルールが多く存在するんです。
NBAにおける「ヘッドコーチチャレンジ」は、使用できる回数がなんと最大2回。
1回目のヘッドコーチチャレンジが成功した場合は、2回目の要求をすることができるんです。
ヘッドコーチチャレンジをする際にはFIBAと同様に「タイムアウト」が残っている必要があり、判定が覆った場合にはタイムアウトが変換されるルール。
ただし、試合時間が長くなることを考慮し、2回目のヘッドコーチチャレンジの際には、判定が覆った場合でもタイムアウトは変換されないことに注意が必要ですね。
また、要求は試合中いつでもすることが可能ですが、要求できる判定の内容は以下の4パターンのみと決まっています。
これも特殊な条件ですが、観客が試合を楽しむためにできるだけ試合を止めないというNBAのエンタメ性が発揮されているポイントと言えるでしょう!
【NBAでヘッドコーチチャレンジが可能な判定】
- 自分のチームに対するパーソナルファウル
- アウトオブバウンズ
- ゴールテンディング
- バスケットインターフェア
「アシスタントレビュー」とは?
アシスタントレビューとは、別室にいる「リプレイアシスタント」がリプレイ映像を確認し、専門的な視点からインスタントリプレイが必要かどうかを判断することを言います。
システムが導入されたのは意外と最近で、2023年のルール改定以降のことだそうです。
審判が自身の判定を確認したい場合に使用されるシステムで、主に試合時間残り2分以内の勝敗を分ける重要な局面で、試合を正当に判定するための仕組みとして導入されました。
新設されたシステムで改善された点
先述したように、2023年以降にFIBAの「ヘッドコーチチャレンジ」ルールが改定されました。
改定された主な点は以下の3つ。
【新設されたヘッドコーチチャレンジの変更点】
- ヘッドコーチチャレンジの回数が①1試合に1度のみという制限がついた。
- リプレイアシスタントの新設でより厳正な判定が可能になった。
- タイムアウト中にチャレンジが発動された場合、タイムアウト終了後にIRSレビューの時間が取られる。
まとめ
今回は「インスタントリプレイシステム(IRS)」や「ヘッドコーチチャレンジ」の仕組みについて解説してきました。
いかがでしたでしょうか?
バスケットボールは高速でボールが行き来するスポーツですから、プロの審判でも正確に判定するのが難しい場面がどうしてもあります。
それを機械の力で解決した「インスタントリプレイシステム(IRS)」は革命的ですし、バスケットボールをより公正で面白いスポーツに進化させてくれたと思います。
ルールを理解することで、バスケの観戦はより楽しいものになるはず!
この記事がみなさんのバスケ観戦に少しでもお役に立てれば幸いです。
それではまた、次の記事でお会いしましょう!