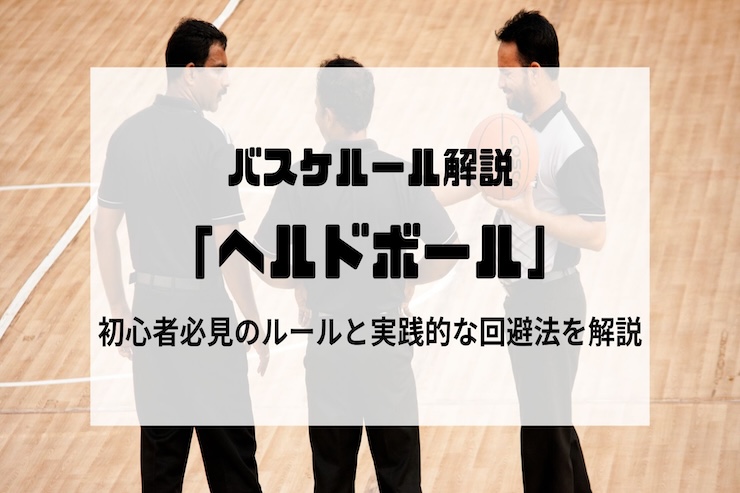こんにちは!
NBA好きブロガーのおしょうサンドです。
みなさんはバスケの「ヘルドボール」とはどのような状態かご存知でしょうか?
試合中に何度も見られるシーンではあるものの、その内容や実際に起きた時の試合の進め方についてしっかりと理解をしている方は意外と少ないのではないかと思います。
この記事では「ヘルドボール」というバスケのルールについて、その内容や起きた時の試合の進め方をはじめ、原因や実用的な回避法についてまで詳しく解説していきます。
試合の進行や勝敗に関わる重要なルールですので、しっかりと理解したい方は必ず最後までご覧くださいね!
それでは早速、ティップオフ!!
目次
バスケのヘルドボールとはどんな状態?基本ルールを解説
バスケの「ヘルドボール」とは、”両チームの選手たちがボールを保持していて、どちらのチームのボールとも言えない状態”をいいます。
子供がおもちゃを取り合っている状況を想像してください。
ほぼアレです。
接戦な状況では両チームともボールを奪うために必死になりますから、バスケの試合では意外と多く見られるシーンの1つです。
具体的には以下のようなケースが挙げられますよ。
【ヘルドボールになるケース】
- リバウンドの際、2人以上の選手たちがボールを掴み離さない。
- スティールしようとしたディフェンスと守ろうとしたオフェンスが同時にボールを掴む。
- 転がったボールを2人以上の選手たちが掴む。
なお、ボールがゴールとボードの間に挟まるなど、どちらのチームのボールでもない状況を含めてヘルドボールと解説している場合もありますが、これは誤りです。
そういった状況とヘルドボールは総じて「ジャンプボールシチュエーション」と呼ばれ、同様の対応が取られるため混同しがちですが覚えておきましょう!
ヘルドボールの状況になると、試合が一時的に中断。
その後、あとで解説する「オルタネイティングポゼッションルール」に従い、どちらかのチームのスローインで試合が再開されるという流れになります。
ヘルドボールになると試合はどうなる?
続いては、実際の試合で「ヘルドボール」になると、どのように進行するのかについて解説していこうと思います!
キーワードは「オルタネイティングポゼッションルール」と「ジャンプボールシチュエーション」です。
ヘルドボールになった場合は原則「オルタネイティングポゼションルール」に則り再開
2025年9月現在、FIBA(国際バスケットボール連盟)は”ヘルドボールには「オルタネイティングポゼションルール」に則り試合を再開する”と定めています。
FIBAが管轄している国際試合はもちろん、日本の国内リーグであるBリーグもこのルールを採用しているようですね!
「オルタネイティングポゼションルール」とは、簡単にいうとボールの保持権を両チームへ交互に与えるルールのこと。
どちらのチームのボールかわからないのなら、公平になるように支配権を決めるルールを作っちゃおう!というわけですね。笑
ヘルドボールになると「オルタネイティングポゼションルール」によってボールを持つチームが決定。
その後、ヘルドボールが発生した場所から最も近い「サイドライン(コートの外枠の長辺)」か「エンドライン(コートの外枠の短辺)」のいずれかからのスローインで試合再開となります。
ちなみに、アメリカの男子プロバスケットボールリーグ「NBA」では「オルタネイティングポゼションルール」の代わりに「ジャンプボール」が採用されています。
NBAのルールについては後ほど解説しますので、興味のある方は参考にしてくださいね!
「オルタネイティングポゼションルール」とは?
では「オルタネイティングポゼッションルール」とは具体的に何なのでしょうか?
オルタネイティングとは英語で”交互に”を意味し、その名の通り各チーム交互にポゼッション(ボールを持つ権利)を与えるルールとなっていますよ。
オルタネイティングポゼッションルールが発動するのは「ジャンプボールシチュエーション」と呼ばれる場面。
「ジャンプボールシチュエーション」はヘルドボールをはじめ、ボールがゴールとバックボードの間に挟まってしまった場合などのようにどちらのボールか決めることができない状態のことを指す用語です。
かつては「ジャンプボール」という各チームの代表選手が空中に投げ上げられたボールを取り合うプレイでスタートしていましたが、試合をスムーズに進めるという目的でオルタネイティングポゼッションルールが導入されたという背景がありますよ。
ではどのようにボールを持つチームを決めているかというと、ここにはポゼッションアローという矢印の存在が関係しています。
ポゼッションアローはタイマーや得点を管理する係の方が操作する矢印であり、試合中に次の「ジャンプボールシチュエーション」でボールを持つ方のチームのゴールを指し示しています。
最初にポゼッションアローが動くのは試合開始のジャンプボールのあと。
ジャンプボールでボールを持つことができなかったチームのゴールを指した状態でスタートしますよ。
その後、ヘルドボールなどのジャンプボールシチューエーションや各クォーターの開始のたびに矢印の向きが切替わり、結果として両チームにとって平等にボールが行き渡るような仕組みになっているというわけです。
「オルタネイティングポゼッション」についてはより詳しく解説した記事がありますので、ルールをしっかり把握したいという方は是非参考にしてみてくださいね!
NBAは「ジャンプボール」で再開される
FIBAがオルタネイティングポゼッションルールを採用してからというもの、多くのリーグが同様のルールを導入しています。
しかし、アメリカの男子プロバスケットボールリーグ「NBA」だけは現在でも「ジャンプボール」を採用しているんですよ。
先ほども解説したように、「ジャンプボール」とは両チームの代表選手(ジャンパー)が審判によって上空に投げ上げられたボールを取り合うプレイのこと。
NBAの場合、ヘルドボールのような「ジャンプボールシチュエーション」が生じた際には、プレイが起こった場所から最も近いサークル(センターサークル、フリースローサークル)でジャンプボールを行うことで試合を再開するというわけです。
ちなみに、NBAが「オルタネイティングポゼッションルール」を採用しない理由は、ジャンプボールの方が個人のスキルと運動能力の競り合いを重要視するNBAの方針と合致しているからだそう。
より高いジャンプ力と空中でボールをコントロールする能力をもった選手がボールを獲るのが”NBA流”というわけですね。
さすがは世界最高峰のリーグといったところでしょう。
ヘルドボールの審判のジェスチャーは?なりやすい具体的な事例も紹介
続いて、ヘルドボールを示す審判のジェスチャーとそのジェスチャーが発動されやすい具体的な事例をご紹介していこうと思います。
これらを知っておくことで試合の流れを予想できたり、審判がヘルドボールをコールした時に何が起こったのか理解することができたりするため、バスケ観戦がより楽しいものになるはずですよ!
ヘルドボールの審判のジェスチャーは?
「ヘルドボール」の審判のジェスチャーは両手の親指を立てた「サムズアップ(いわゆる”グッド!”)」の形。
審判はこのジェスチャーとともに「ヘルドボール!」と叫ぶことで、選手やテーブルオフィシャルに試合の一時停止とフリースローによる再開を伝えることができますよ。
※テーブルオフィシャル:タイマーや得点などの係員の総称
ヘルドボールになりやすい具体的な事例3選
長く試合観戦をしていると、だいたいそのプレイが起きそうなシーンを予想できるようになってきますよ。
ヘルドボールも試合中何度かはおきがちなシーンですが、中でも特に起きやすい状況を3つご紹介しようと思います。
次の観戦時にはこれらの状況を予測しながら観戦をしてみると、選手たちのプレイの意図がわかってくるかもしれませんね!
①リバウンドの奪い合い
リバウンドの際、両チームの選手たちが同時にボールを掴み離さない。
②1オン1のプレイ中
ディフェンスが直接ボールを狙ったスティールをしようとした際にオフェンスがボールを掴み、2人同時にボールを掴む形になる。
③キャッチミスなどで転がったボールの奪い合い
味方のパスをキャッチできず転がったボールに対し、両チームの選手たちが同時にとびつき奪い合いになる。
ヘルドボールが多発する原因7選
ヘルドボールは相手にボールが渡ってしまう可能性も高く、ボールを持っているチームにとってはできるだけ避けたい状況ですよね。
しかし、ヘルドボールは試合中に何度も発生してしまうもの。
そこでここからはヘルドボールが多発してしまう原因を7つ簡単にご紹介していこうと思いますよ。
【ヘルドボールが起こる原因7選】
- ボール保持スキルの未熟さ
- 判断の遅さ
- ディフェンスの積極的なプレッシャー
- チームのサポート不足
- ルーズボール時の争い
- 試合展開の遅さ
- インサイドエリアでの攻防
ボール保持スキルの未熟さ
ボールを保持するスキルが不足しているとヘルドボールになる可能性が高くなります。
ディフェンスにボールをとられないためには、相手から遠ざかりながらドリブルをしたり、ディフェンスとボールの間に自分の体を入れ込む形でドリブルをしたりとボールをとられないようなドリブルスキルが必要になりますよね。
ミニバスやバスケを初めて間もない方はそのようなスキルがなく、ディフェンスにボールをつかまれてヘルドボールになることが多いです。
判断の遅さ
「判断の遅さ」もまたヘルドボールになる要因の1つです。
バスケではボールを持った時、主に「パス」、「シュート」、「ドリブル」の3つの選択肢があります。
試合中は味方と相手の動きを見ながらこれらの選択肢を素早く判断していく必要があるわけですが、この判断が遅いとディフェンスにとっても非常に守りやすくなってしまいます。
結果的にディフェンスにボールをつかまれる可能性が高くなり、ヘルドボールも起きやすくなりがちです。
ディフェンスの積極的なプレッシャー
これは少し上級者向けですが、「相手の積極的なプレッシャー」によってもヘルドボールの可能性は高くなります。
相手が非常にディフェンスがうまく、特に要所でダブルチーム(1人のプレイヤーを2人でディフェンスすること)をしてくる場合、オフェンスのボールコントロールは非常に難しくなります。
プレッシャーで身動きが取れなくなったオフェンスに対し、ディフェンスがボールを掴みにかかりヘルドボールとなるのはよくあるシーンです。
チームのサポート不足
「チームのサポート不足」もまたヘルドボールの大きな要因の1つ。
ボールを持っている選手はどうしても高いプレッシャーを受けがちですよね。
そんな時、チームメイトがパスを出せる位置にいないと選択肢が狭まり、ディフェンスにとっても狙いやすい状況になってしまいます。
結果的に孤立したプレイヤーがディフェンスにつかまり、ヘルドボールになるというわけです。
ルーズボール時の争い
「ルーズボール時の争い」もヘルドボールにつながる可能性が高いです。
ルーズボールとはどちらのチームも保持していない状態のボールのことで、激しい接触プレイやパスミスなどにより生じることがある現象。
リバウンド(シュートが外れ、リングに当たって跳ねた状態)もルーズボールの1種だそうですよ。
ルーズボールが発生すると、敵味方関係なく複数人が同時にボールに飛びつきにかかるため、ヘルドボールになるケースが多くあります。
試合展開の遅さ
「試合展開の遅さ」もヘルドボールの要因になります。
試合展開が遅いということは、1回の攻撃にかかる時間が長いということ。
攻撃にかかる時間が長ければディフェンスと接触する回数も多く、その分ディフェンスがボールを狙う機会も多くなりますよね。
特に女子バスケやミニバスでは試合展開が遅くなりがちで、ヘルドボールにつながるケースが多くあります。
インサイドエリアでの攻防
「インサイドエリアでの攻防」もまたヘルドボールになるきっかけの1つです。
インサイドエリアでは複数人のプレイヤーが接触するシーンが多く、選手同士の距離が近いのでディフェンスがボールを掴みやすい状況になります。
また、リバウンドの取り合いでも複数のプレイヤーが同時にボールに触る機会があり、そのままヘルドボールになるのもありがちなケースと言えるでしょう。
ヘルドボールを避ける方法6選
さて、ヘルドボールの原因の中に自分に当てはまるものはあったでしょうか?
ヘルドボールを避けるためには自身のスキルアップはもちろん、チームでの結束も重要だということがわかっていただけたと思います。
ここからはそんな「ヘルドボール」を避ける方法について解説していきます。
どれも意識して練習すればできるようになることですので、ぜひ参考にしてみてくださいね!
【ヘルドボールを避ける方法6選】
- 早めのパスでボールの保持時間を短くする
- フェイクを活用しディフェンスとの接触を避ける
- ボールを保持する位置を変えディフェンスから遠ざける
- 視野を広げ味方の位置や空いているスペースを把握しながらプレイする
- チームメイトとの連携を強化しパスコースを確保する
- フットワークを鍛えディフェンスを回避する
早めのパスでボールの保持時間を短くする
1人のプレイヤーがボールを持っている時間が長ければ長いほど、ボールの移動が少なくディフェンスにとっては守りやすい状況となります。
ディフェンスが距離を詰めてくる前に早めのパスを出すように心がけることで、ヘルドボールの回避につながるはずです。
フェイクを活用しディフェンスとの接触を避ける
少しレベルが高いですが、フェイクの活用もまたヘルドボールを減らすことにつながります。
オフェンスのすることがディフェンスに読まれてしまうと、そのまま狭いスペースに追い込まれてボールを奪われてしまう可能性が高まりますよね。
シュートフェイクやパスフェイクを活用してタイミングを外し、ディフェンスにボールへ飛びつくのは危険だと感じさせることが重要です。
ボールを保持する位置を変えディフェンスから遠ざける
ヘルドボールを避けるうえで最も重要なことの1つが、ボールの保持する位置をディフェンスから遠ざけることです。
ディフェンスとボールの間に自分の体を入れてボールを守ることができれば、ディフェンスはボールに触ることが難しくなりますよね。
重心を落とし、低い姿勢でボールをコントロールできるようになれば、ディフェンスにとって非常に守りづらい状況を作ることができるはずですよ!
視野を広げ味方の位置や空いているスペースを把握しながらプレイする
これはかなりレベルが高いですが、視野を広げ、見方や相手の状況を把握しながらプレイをすることでヘルドボールを回避することができます。
ディフェンスにプレッシャーをかけられた状況であっても、空いたスペースや味方の位置を把握していればドリブルやパスで状況を打開することができますよね。
これを実現するためには、顔を挙げた状態でボールをキープするドリブルスキルや相手の動きを読むための戦術学習などが必要になります。
チームメイトとの連携を強化しパスコースを確保する
チームメイトとの連携強化でパスコースを確保することによってもヘルドボールを回避することができます。
先ほどお伝えしたように、ボールを持っている選手が孤立してしまうとディフェンスにとっては非常に守りやすい状況になってしまいます。
チームメイトと話し合い、見方が孤立しないようにポジションを変えていつでもパスを出せる状況を確保しておきましょう!
味方がダブルチームをされているときにうまくパスを出すことができれば、一気にチャンスにつなげることができるかもしれませんよ。
フットワークを鍛えディフェンスを回避する
最後はかなり基礎的な回避方法ですが、「フットワークを鍛えること」もかなり効果的だと言えるでしょう。
特に試合終盤には疲れもたまって足が動かなくなってしまうと思いますが、足が止まってしまうとディフェンスにとっては格好の的にされてしまいますよね。
ディフェンスをかわせるアジリティ(敏捷性)のトレーニングはもちろん、試合を通じて素早く動き続けられるスタミナのトレーニングも行うことで、ヘルドボールの発生率を大幅に減らすことができるはずです。
ヘルドボールのルール|ミニバスの場合
小学生以下のプレイヤーがプレイする競技である「ミニバス」。
幼稚園から小学校高学年までのプレイヤーが参加する都合上、一般のルールではどうしても試合がうまく進行しないことがあります。
「ヘルドボール」についてもプレイヤーの成長と安全に配慮し、ミニバス独自のルールで運用されているので簡単にご紹介しますね。
ミニバス特有のルール運用
ミニバスでは、一般的なバスケに比べて「ヘルドボール」となる状況が非常に多いという特徴があります。
ヘルドボールが多い理由はあとで説明しますね。
このため、ミニバスでは選手の成長と安全に配慮し、以下の2つの”共通認識”のもとでルールが運用されていますよ。
- 公平なオフェンス機会の保証
- 審判による早めの試合中断
当然なんとなくやっているわけではなく、それぞれこんな意図があるんです。
【公平なオフェンス機会の保証】
ミニバスの最大の目的は、選手たちにバスケを楽しみながら成長してもらうことにあります。
このため、両チームが公平にオフェンスとディフェンスを行うことができるよう、”オルタネイティングポゼッションルール”が非常に重要視されているんですよ。
※オルタネイティングポゼッションルール:試合を公平に進めるため交互にオフェンスの権利を与えるルール。
【審判による早めの試合中断】
バスケを初めたばかりのプレイヤーも多くプレイするミニバスでは無理な接触から大きな喧嘩になってしまうこともしばしば。
安全性を確保するため、ヘルドボールのような”ボールの取り合い”になった場合は審判が早めに笛を吹いて試合を止める傾向にあるというわけです。
ミニバスでヘルドボールが多い理由
ミニバスで「ヘルドボール」が多い理由は非常に明確。
まだスキルや経験が未熟な選手が多く、ボールをキープする能力が不十分だからです。
ただ前にドリブルするだけならできたとしても、相手のディフェンスを潜り抜けながら8秒以内にフロントコートまでボールを届けるとなると様々なスキルや判断が求められますよね。
ミニバスでは特に強いプレッシャーをかけられたときにボールが手から離れてしまうプレイヤーが多く、ヘルドボールになりやすいというわけです。
ヘルドボールのルール|3×3(スリーオンスリー)バスケの場合
続いて、2021年に開催された東京オリンピックにて競技種目として採用された「3×3(スリーオンスリー)バスケ」についても見ていきましょう!
通常のバスケットボールよりも狭いコートで行われる「3×3(スリーオンスリー)バスケ」ではヘルドボールが頻発します。
試合に停滞感を与えないよう、簡略化されたルールとなっているのが特徴ですよ。
3×3(スリーオンスリー)特有のルール運用
先述したように、「3×3(スリーオンスリー)バスケ」ではヘルドボールが非常に多く発生します。
コート自体が狭く、接触プレイが多く起きるためですね。
もしヘルドボールが発生した場合には、3×3(スリーオンスリー)バスケ特有の「チェックボール」というプレイが行われ、攻守を交代して試合再開となりますよ。
即試合を再開することができ、ゲームのスピード感を失わせないためのルールというわけですね。
「チェックボール」についての公式の定義を載せておきますので参考にしてくださいね!
第17条 チェックボール
17-1 定義
17-1-1
ボールがデッドになった後でどちらかのチームに与えられるポゼッションは、アーク外側ののコートのトップでボールを(ディフェンス側からオフェンス側へ)受け渡すチェックボールで始まる。
3×3(スリーオンスリー)では戦術的な影響が大きい
3×3(スリーオンスリー)バスケ特有のヘルドボールのルールは、戦術的に大きく影響しています。
ヘルドボールになれば自動的に攻守変更となるため、個人スキルがより重要で、ボール奪取能力や保持力が試合の結果に直結しているというわけです。
まとめ|ヘルドボールとは?
今回は「ヘルドボール」についてルールとや起きる原因、実践的な回避法を解説してきました。
いかがでしたでしょうか?
この記事のポイントをまとめると以下の5つになります。
【この記事のポイント5選】
- ヘルドボールとは両チームの選手が同時にボールを掴み、どちらのチームのボールかわからない状態を指す。
- FIBAのルールでは、ヘルドボールの際はオルタネイティングポゼッションルールに従いボールの保持権を決める。
- NBAではFIBAとは異なり、ジャンプボールにてボールの保持権を決める。
- ヘルドボールの審判んジェスチャーは両手で「サムズアップ」のポーズ。
- 身体能力やチーム力の低さがヘルドボールの原因になりやすいため、普段から意識をして練習をすることで避けることができる。
バスケのルールを深めることで、プレイや試合観戦をより深く楽しむことができるはず。
このサイトではバスケのルールについて初心者の方でもわかりやすいように解説していますので、他のルールについてもしっかりと理解をしたい方は是非参考にしてくださいね!
それではまた次の記事でお会いしましょう!